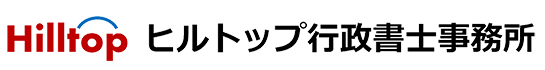フリーランス法違反による勧告
2025年6月26日
ご訪問ありがとうございます。 豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。 昨年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法 […]
支部研修会(相続・遺言)
2025年3月23日
ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。 昨日は、所属する南・港南支部の業務研修会が開催されました。 講師は湘南支部の我妻(あづま […]
- カテゴリー
- その他の業務
リーガルチェックあるあるPART15(Wordコメント機能)
2025年1月30日
ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェック専門「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。 今回は、リーガルチェックのあるあるです。 リーガルチェックをする際に、Wordのコメント機能を […]
- カテゴリー
- リーガルチェック
リーガルチェックあるあるPART14(統一性がない契約書)
2025年1月24日
ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成やリーガルチェックに精通した「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。 今回は、契約書のリーガルチェックについてのあるあるです。 契約書のリーガルチェックをし […]
- カテゴリー
- リーガルチェック
明けましておめでとうございます。
2025年1月6日
ご訪問ありがとうございます。豊富な企業法務経験による契約書の作成リーガルチェックを提供する「ヒルトップ行政書士事務所」の濱村です。 明けましておめでとうございます。 本日9:00から営業を開始しますので、よろしくお願いい […]
- カテゴリー
- ひとりごと