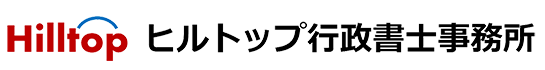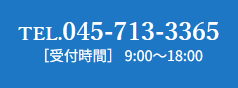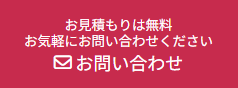ハードウェア(機器・装置・サーバー)保守契約書を徹底解説!
最終更新日:2025年12月24日
ハードウェア保守契約書は、ユーザが導入した機器・装置・サーバー・ルーターなどが故障した際に、故障修理・交換対応・復旧対応を依頼する契約となります。
ハードウェアは導入して終わりではなく、運用できる状態をキープすることが求められるため、しっかりと保守契約書を締結しておくと安心です。
保守の内容、保守範囲や費用負担をあいまいにしておくと、トラブルが生じることにつながります。
特に、委託料の中で、どこまで対応してもらえるか(対応するか)を明確にしておく必要があります。例えば、オンサイト対応を保守料金に含めるのか、それとも別料金になるのかなどが想定されます。
※ソフトウェア・アプリの保守契約書については、こちらをご確認ください。
ハードウェア保守契約書の概要
「ハードウェア保守契約書」とは、導入したサーバ、ルータなどのハードウェア(機器)が故障した場合、ハードウェアの故障修理や交換を委託したり、これらのサービスの提供を行うための契約書です。
特に、突然のハードウェアの故障による運用停止により、業務への影響を可能な限り抑えたい場合、休日や深夜に緊急対応を依頼しても対応できませんので、ハードウェア保守契約書を事前に締結することにより、ハードウェアメーカー技術員の緊急な復旧対応(24時間365日)を受けられるのです。
また、ハードウェア保守には、ハードウェアを常に正常な状態で運用したり、ハードウェアの故障の未然防止・円滑な運用を維持する目的で行う定期点検を含むこともあります。
ハードウェア保守契約書の特徴
ハードウェア保守は、既に運用しているハードウェアについて行うものです。ハードウェア保守契約書の特徴は以下のとおりです。
- 既に運用中のハードウェアが対象となります。
- 必ずしもハードウェアメーカーと保守契約を締結するとは限りません。
- 通常1年間の契約不適応責任があり、契約不適合責任の範囲内で対応してもらえますが、故障時の早期復旧のため、ハードウェア保守契約を締結することが多いです。
- ハードウェアを復旧させることが目的となるため、原則として仕事の完成責任を負うことが想定され、請負契約となることが多いです(この場合、契約不適合責任を負います)。
- 請負契約となる場合、ハードウェア保守契約書には収入印紙の貼付が必要となり(第2号文書・第7号文書など)、契約金額や期間の記載に注意が必要です。
ハードウェア保守の業務やサービスの内容
ハードウェア保守の業務やサービスの内容は、保守会社ごとにかなり差があります。契約書では、どの業務やサービスを対応してもらえるか明確にしておくことが重要です。一般的には、次のような内容があります。
故障対応業務
ハードウェア保守契約書で最も重要となるのが故障対応です。
ハードウェアが停止したり、不具合がある場合、可能であれば、遠隔で現在の状況確認を行い、原因の切り分けを行います。
ハードウェアに原因があるとした場合、復旧可能かを確認します。
具体的には故障修理・部品交換・ハードウェアごとの交換を行うことがあります。さらに故障対応に伴い、ハードウェアに再設定を行うこともあります。
この故障対応では、メーカー保証の範囲内か、別途有償になるのか、保守料金に含まれるのかを明確にしておく必要があります。
定期点検
定期点検は、いわば、故障を予防するための保守です。
内容としては、外観の確認、内部清掃、冷却ファンの動作確認、基板の状態、ケーブルのゆるみ、異音の有無、温度上昇の確認などが挙げられます。
定期点検はあくまで「状態確認」ですので、故障修理とは異なります。
よくある誤解は、定期点検時に発見された不具合を定期点検費用の範囲で、無償で修理してもらえると委託者が期待してしまうことです。
定期点検と故障対応は別であり、別途故障対応費用がかかることを明確にしておく必要があります。
●ハードウェア保守契約書作成をご検討の方へ
保守契約書を新規で作成したい場合は、当事務所の契約書作成サービスページをご覧ください。
保守業務委託契約書、保守サービス提供契約書、保守サービス利用規約(申込書付き)、保守基本契約書(注文書請書付き)、スポット保守契約書など保守契約書に数多くの実績があります。
ハードウェア保守の故障対応の種類
主なハードウェア保守の故障対応の種類は以下のとおりです。
オンサイト
・保守会社が自社の技術者を現地に駆け付けさせ、故障対応を行い、早期に復旧させます。
現地に駆け付けさせるには、24時間対応など人員の確保に経費がかかりますので、一般的に高額です。
また、駆け付け目標時間を定めることもあります。
センドバック
・ハードウェアを使用しているユーザが故障したハードウェアをメーカに送付し、修理後返却してもらい、自ら設置設定などを行います。
※一般的にサービス料金は抑えめですが、時間がかかり、故障修理の期間、使用できなくなることが問題となります。
先出しセンドバック
・故障申告を受けた場合、ハードウェアのメーカが事前に準備したハードウェアを現地にすみやかに送付し、ユーザが自ら故障したハードウェアと交換し、故障したハードウェアをメーカに送付し、修理を依頼するものです。
修理が終わった後、次の故障に備えて、予備のハードウェアとして準備しておくこともあります。
オフサイト
・文字通り、上記のオンサイトの逆のことを指していて、ハードウェアの故障が発生した現地から離れた外部(通常は保守会社の拠点)において故障対応を行うことを言います。具体的には、電話やメール、リモートアクセスによる対応などを指します。
ハードウェア保守契約書作成のポイント
ハードウェア保守契約書作成のポイントをまとめてみました。どれも実務に長年携わってきた経験に基づいています。参考にしてください。
保守の対象
保守の対象を明確に定めましょう。
どのハードウェアなのか、メーカー、型番、製造番号などを記載しているか、具体的に定めないと後日もめることにもなりかねません。
継続的な契約
保守契約は継続的な契約です。
複数年契約の場合もありますが、通常1年契約であることが多く、更に、契約事務処理軽減のため、自動延長条項を定めておくことが多いです。
報告
保守契約では、納入品を納入することがありませんので、業務(=仕事)の完成したことを証する書面として、報告書を提出いたします。これを検査して、仕事が完成したことをチェックします。但し、センドバックでは、修理済み品に同封される納品書が報告書となります。
支払
保守契約は、継続的な契約であるが故に、以下のとおり、様々な支払パターンがあります。
- 一括払い(前払い・後払い)
- 月払い(前払い・後払い)
-
四半期払い(前払い・後払い)
- 半年払い(前払い・後払い)
- 1年毎払い(前払い・後払い)※複数年契約の場合
などがあります。
この他にも、1年目と2年目で期間や金額が異なることもありますし、1年目は0円、2年目は通常の金額ということもあります。当事務所では、様々な取り決めに対応可能です。
インシデント
契約期間中に業務の上限回数を定めておき、その回数を超えたら、インシデント(チケットのようなもの)を購入するという対応をインシデント対応ということがあります。
これは無制限に業務を実施するのではなく、想定される回数や過去の実績ベースで算出して、経費の節減につながるという効果があります。
なお、契約期間満了時に、インシデントがまだ残っている場合でも、次年度以降には繰り越されないとすることが多いです。
非定額業務(オンサイト)
実施することが想定されないものの、保守内容や単価などを定めておき、実際に、そのような保守を行うと、あらかじめ定めておいた単価で算出した料金が発生するというものです。
特に、オンサイト対応を実施した場合に、別料金となることが多く、契約金額とは別にオンサイト料金を支払うということになります。
これも当初の契約金額にオンサイト料金を乗せていないので、実際にかかった場合にだけ支払えばよいので、経費節減につながります。
保守対象外業務
天災地変など不可抗力で発生した業務、保守業務の対象外となる業務、また契約書に記載していない業務を実施した場合は、別途料金がかかるとするものです。
何もなければ保守業務の範囲が広くなってしまいますので、このような規定を設けることで、業務の線引きが可能となります。
また、特に受託の場合、ユーザの立場のほうが強いケースが多いですから、あらかじめ明記することで別途料金がかかると主張しやすくなります。
変更契約
保守契約は継続的な契約であり、自動延長が5,6年繰り返されるということがほとんどです。
そのため、契約金額、単価、条件などを変更契約を締結することで変更することになります。この場合、収入印紙が問題となってきます。
「秘密情報」や「個人情報」の遵守に関する覚書
継続的に「秘密情報」や「個人情報を取り扱うことになりますので、その取扱いや情報事故が生じた場合の手続き、損害賠償などを取り決めた「秘密情報」や「個人情報」に関する覚書を、保守契約書とは別に締結することが多いです。
これは、情報漏えい事故があると、某B社の例を見ても分かるように、ユーザが莫大な損害を被ることになりますので、大企業から受託する場合、特に増えております。
一般的に、これを遵守していないとは言えない内容ですので、委託先としては受け容れざるを得ないのですが、よく見ると会社として対応できない内容もありますので、委託元から提出される書式をしっかりチェックする必要があります。
ハードウェア保守契約書の印紙
ハードウェア保守契約書のうち、「継続的な請負契約」に該当するものについては、印紙税法上、第2号文書(請負に関する契約書)になりますが、「契約期間が3か月以内で、かつ自動更新のないもの」を除き、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当することとなります。
この場合、どちらの文書に所属するかは、以下のとおり契約書に記載金額の記載があるかどうかで決定されることとなります(通則3のイ)。
●契約書に記載金額の記載がある場合(契約金額と契約期間の記載があり契約書上で契約金額が明確な場合)
→第2号文書(印紙税額は、請負契約の契約金額により決定されます)
●契約書に記載金額の記載がない場合(契約金額と契約期間のうち、両方又はいずれかの記載がないため、契約金額が不明確な場合)
→第7号文書(印紙税額は4,000円)
収入印紙を貼付していない場合でも、ハードウェア保守契約書の有効性に影響がある訳ではありませんが、印紙税額の3倍の過怠金がかかりますし、企業としての信用力の低下となる場合も想定されますので、ご注意ください。
サービス案内
- 契約書の作成を希望する方契約書作成サービス
- 契約書のリーガルチェックを希望する方契約書リーガルチェックサービス
- 契約書の定額チェックを希望する方契約書定額チェックサービス
ハードウェア保守契約書の作成・チェックにお悩みの方へ
当事務所では、ハードウェア保守契約書・ハードウェア保守ライセンス規約の作成やチェックの依頼をこれまで数多く受けてまいりましたが、保守の対象、保守業務や保守サービスの内容などの記載が曖昧なものが多いと痛感しています。
これらを明確に記載することで、保守業務や保守サービスの性質が請負なのか、準委任なのか、はたまた単なる情報提供なのかが判断できることになり、委託を受ける保守会社の責任範囲が明確になり、これによって保守契約書の作成に着手できることになります。
契約書に、単に保守業務や保守サービスを羅列することが多く、本来あるはずの業務やサービスの連続性が表現されず、結果わかりにくい契約書になっていると感じています。
また、保守契約では納入品がないにもかかわらず、納入品や所有権・著作権の譲渡に関する条項の記載があるなど、よくある「開発・納入型」の業務委託契約書で締結してしまい、本来必要な条項が欠落し、不要な条項が規定されているという、実際とマッチしていない契約書も非常に多く見かけます。
当事務所は、お客様からのヒアリングを最も重視しており、しっかりと意思疎通を図ることで、より詳細かつ明確、そして、保守業務や保守サービスの連続性のある保守契約書を作成したり、そのような保守契約書となるようリーガルチェックいたします。
これによって、長期間にわたり継続する保守契約を安心し締結し、運用していただけるようお手伝いしたいと思っています。
保守契約書のリーガルチェックQ&A
保守契約書のリーガルチェックに関するQ&Aについて、まとめてみました。
- リーガルチェックでは、どこまで確認してもらえますか?
- 以下の点に気を付けて確認いたします。
・一方的に不利な条項が含まれていないか
・契約実務上トラブルになりやすい条文がないか
・契約書全体として内容の不整合がないか
・不足している条項がないか
ただ、問題があるかのリスク診断だけでなく、「具体的にどのように修正すればよいか」まで確認いたします。 - 契約相手から提示された契約書でもチェックしてもらえますか?
- はい、可能です。
非常に多いご相談で、以下のようなお悩みを抱えている方が非常に多い印象を受けます。
「このまま署名押印して問題ないか」
「どこまでなら修正を求めてよいか」
実際、契約相手から提示された契約書の場合、契約相手に一方的に有利な条項が数多く含まれていることが多いです。
当事務所では、臆することなく、お客様が不利になることがないようリーガルチェックを行います。
●保守契約書・保守基本契約書などの作成や見直しはお見積り無料!
保守契約書、保守基本契約書、保守規約・約款などの作成や見直しは、内容を確認したうえで無料お見積りできます(最短30分)。